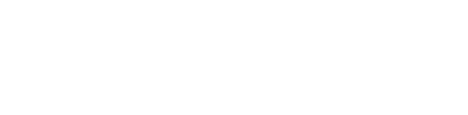今回はPS1のある意味不遇の名作アクションRPGである『ブレイヴフェンサー 武蔵伝』について語る。
PS1に名作数あれど、この『武蔵伝』は私のPS1名作ランキングの五指に入ることは間違いない。
本作は1998年7月16日にPS1でスクウェアから発売され、2018年7月15日には20周年を迎え、スペシャルムービーも公開されている。
キャッチコピーは『でっかいシリーズ始めます』。
Contents
ゲーム概要:コミカルとシリアスが同居した世界観をもつアクションRPG
本作はかの有名な二刀流の剣豪・武蔵が主人公のアクションRPG。
自由に移動できるマップは、ストーリーの進行に合わせて実行できるアクションが増え、それに応じて舞台も広がっていく。ストーリー自体は一本道であるものの、なかなか自由度の高いゲームである。
物語は武蔵が「ヤクイニック王国」のフィーレ姫に英雄召喚と言われる異世界召喚術で呼び出されるところから始まる。
王と王妃の不在中に攻めてきた「ル・コアール帝国」から守ってほしいと懇願され、伝説の剣レイガンドと城に代々伝わる雷光丸の二刀流で帝国と闘っていく。
この武蔵は以前にも呼び出されたことがあり、今回が2度目の召喚となるのだが、召喚を行ったフィーレ姫が未熟だったため召喚に失敗し「ムサシ」と名乗る子供が召喚されることとなった。
この辺りの設定は最近流行のなろう系異世界モノに通じるものがあり、時代の先取り感がある。武蔵以外にも佐々木小次郎や、五右衛門・弁慶なども出てくるのでどちらかというと「ドリフターズ」や「Fate」だろうか。
しかし、本作はそれらとはまったく似ても似つかないストーリーとなっている。
開始早々のコミカルな帝国軍の面々など愉快な物語と思いきや、ストーリーは徹底してシリアスでダンジョンや各種イベントはシビアな展開が多い。
主人公の拠点となる城下町の人々を初めとしたサブキャラクター達は陽気な面を見せるが、そのうらでは各々が複雑な背景を持って生活している。
そういった絶妙なバランスの世界観も本作の魅力の一つである。
不名誉な知名度を持つ不遇の名作。『体験版のオマケ』として
本作は中途半端な知名度を誇る。
というのも、当時は本作自体はそこまで注目は浴びなかった。本作についてきた体験版にこそ注目が集まっていたのだ。その体験版とは、かのFF7の次回作であり、知名度も期待度も最高だったFF8、そして大型新作エアガイツだったのである。
その結果、FF8の体験版のオマケというとてつもく不名誉な呼ばれ方をすることになった。
しかしながら、本作をプレイしたプレイヤーは評価を改めることになる。
『武蔵伝』は骨太で画期的なシステムをもつ歯ごたえ十分な名作アクションRPGだったのだ。
そうして本作は最終的に65万本も売れることとなる。
多彩でやり応えのある難易度を誇るアクション
アクションRPGである本作は非常に多彩なアクションが可能となっている。
3Dフィールドを自由に駆け回り、多彩なアクションやスキルを駆使して攻略していく。
特徴なバトルシステム「ゲット・イン」と「五輪の書」
本作の主人公であるムサシはもちろん二刀流で、2種類の特殊な剣を使用する。
それが日本刀「雷光丸」と巨大な伝説の剣「レイガンド」だ。
雷光丸は「ゲット・イン」という相手のエネルギーを吸収し、相手の技を取得する特殊攻撃が行える。そして取得した技「ゲット・イン技」と呼ぶ。
取得できる技には弾を飛ばす「ガンもどき」、相手をスタンさせる「みねうち」のような戦闘スキルの他、特殊ステータスを回復したりトゲ床を無視する「ホッピング」など多岐に渡る。
ほとんどの敵がゲット・イン技を持っているので、新たな敵や強敵と出会うことが煩わしくなく、むしろ楽しみになるのだ。
中にはバッドステータスに陥る罠のような技や、ステージの仕掛けを解くための技などもあり、新たな敵・スキルとの出会いをより刺激的なものへと昇華させている。
そしてレイガンドは各ボスを倒していくことで「五輪の書」と言われる属性を帯びた必殺技を習得する。
五輪の書は攻撃能力が低く、謎解きや新たなフィールドへ移行するために使われるものが多いが、空を飛んだり大地を揺らして足止めしたり炎を出したりと派手なものが多く、修得するたびに心が躍った。
スキルの他にも「伝説の武具」を手に入れると2段ジャンプなどアクションの幅もさらに増えていく。
こういった新しいスキルが戦闘だけでなく、謎解きや新たなステージの開拓にも使えるデザインは「ゼルダの伝説」が近いだろう。
前述した「五輪の書」と合わせ、作品全体を楽しくさせる優秀なゲームデザインである。
また、ムサシは物語の進行や助けた人々から特殊な剣技を覚えることができる。この技も曲者で、ただボタンをセットするだけでなく、たとえば雷光丸とレイガンドで続けて斬ると十文字斬りになったりアクション自体が増えていくシステムになっており、中には投げ技や移動技となるものも存在する。
ちなみに、この世界にはビンチョパワーと言われるエネルギーが存在しており、ムサシ達はその力によって世界に存在することができている。そして雷光丸にはその力を吸収する力が備わっており、それこそが「ゲット・イン」といわれる技なのだ。
これはゲーム開始時に説明されるものなのだが、ゲームの最後まで重要な設定になっており、攻略において重大な伏線にもなっている。
数々のトラウマを産みだした高難易度
このゲームは難易度がかなり高い。
全体で見ると普通のアクションRPGぐらいなのだが、要所要所でトラウマ級の難しさがある。
たとえば有名なところで言えば「スチームウッド」だろう。
一定時間内に吹き出す蒸気を飛び越えながら目的地を目指すのだが判定が異常にシビアなのだ。
かなりギリギリでジャンプしなければならないうえ時間制限が襲い掛かり難易度は加速する。
しかも、このスチームウッドは一度ではなく、何度も暴走してプレイヤーに襲い掛かる。
一度目で苦戦したプレイヤーは二度目のスチームウッドで恐怖したことだろう。その名前を二度と聞きたくなかったプレイヤーも多かったはず。ちなみに筆者はガチで詰み、友達にクリアしてもらった。
他にもラストダンジョンで詰んだというプレイヤーは多いのではないだろうか。やたら難易度が高く長いうえ、突入すると引き返せないため回復アイテムが足りなくなる恐れがあるのだ。
こうなるとはっきり言って詰みだ。
なので、もし今からやることがあるのなら、できるだけ準備を整えて挑んでほしい。
絶望を与える恐怖のトラウマイベント
多くのプレイヤーに絶望を与え、武蔵伝の名を心に刻みこんだものの1つに「ヴァンビ」がある。
ヴァンビとは、青白く変色した体を持ち、豚や蝙蝠のような顔で、巨大な手をした異形な姿の二足歩行吸血生物である。
名前もヴァンパイア+ゾンビであるように、作中ではゾンビのように扱われており、太陽光を浴びると消滅してしまう。知能は低く、遺跡など暗い場所に生息する。あるイベント発生時には夜の城下町を周回し、非常に不気味な存在。
そして物語中盤、ムサシと仲のいい子供がヴァンビに噛まれるというイベントが発生する。
助けるためには時間内に薬を入手しなければならないのだが、なんと失敗しても物語はゲームオーバーとならず進行してしまう。
すると、その子供は本当にヴァンビになってしまい、一部のキャラクターは責任を感じて永久に居なくなってしまうのだ。
一応このルートでも子供は後々治るのだが、治るまで雑貨屋は使えなくなり、治った後も去ったキャラクターは戻ってこない。
しかもこのイベントは難易度が高い。本気でやっても普通に失敗する。
失敗した多くのプレイヤーが「どうせゲームオーバーになるだろう」と油断していたことだろう。
武蔵伝はほのぼのとしたコメディ風な導入に反し、そうした本気の恐怖をプレイヤーに与えるのが上手い作品だったのだ。
住民が画面の向こうで生きて生活していた。時間と曜日の概念をもつリアルタイムな世界
本作には曜日と時間の概念が存在している。
村の住人は時間によって行動が変化する。あるキャラクターは朝になれば散歩をしているし、昼になれば教会に行き、夜になれば酒場で酒を飲み、深夜になると家で寝ているのである。
そしてこれはリアルタイムで行われ、時間の経過と共にキャラクター達は自分たちの生活を謳歌している。
曜日やストーリー進行によっても住民の行動は変化するし、住民キャラクターだけでなく、敵や建物、ダンジョンですらも時間により変化していく。
当時の似たようゲームで言えば「ゼルダの伝説 ムジュラの仮面」が近いだろう。
キャラクター達はみんな活き活きとしていて、そこに一人の人間として描かれていたからこそとても愛着がわくようにできていた。
その愛着ゆえに前述したトラウマとなるイベントもあるのであるが、それはこのよくできた世界観があってこそだと言えるだろう。
また、時間の概念はキャラクターの行動だけでなく、所持アイテムやマップにも影響する。
たとえば、安くて回復効率の良いパンは所持した状態で数日経つと腐ってしまう。逆に、効果の薄い納豆はずっと所持していると発酵して最強の回復アイテムとなる。
お金は結構シビアなため、時間をかけて金を節約したり、村でタダでとれる井戸水で凌いだり、プレイヤーは回復アイテム1つとっても自由な選択を選ぶことができた。
また、ムサシには「眠気」というステータスが存在し、これが貯まると行動に著しく制限がかかり、たとえダンジョンの中であってもお構いなく寝てしまう。
ゆえに、宿屋や野宿を駆使しながら眠気をちょくちょく解消しなければならない。
眠気を取るのが面倒だからと無茶な行動をしていると、あと少しで間に合うはずだった時限イベントに眠気が来てしまい、逆に間に合わなくなるということもよくあった。
バッドルートも存在するイベントでも構わず寝てしまうので、今なら批判の嵐かもしれない。こういったものが許されたのは当時ならではだろう。
こういった不便さもまた世界観を掘り下げるのに一役買っているのだ。
裏も表もある生きたキャラクター達と世界観
本作のキャラクターは生きている。
間違いなく、画面の向こうで彼らは生きているのだ。
牧歌的な世界の住民たちに潜む深みのある背景
ブギーポップでお馴染みの緒方剛志氏によるやわらかで素朴なタッチで描かれるキャラクター達。彼らはとても心地がいい牧歌的な世界観を演出している。
冒険の拠点である「アミヤクイ村」は昔のファンタジー作品によくあるような田舎町だ。そんな世界の住人達は、リアルタイムに流れる時間のなかで自由に生活している。
この時代のゲームには珍しく、ほとんどのキャラクターがボイス持ちなのも命を抜きこむことに一役買っている。
そんなのほほんとした世界観であるが、設定は妙に作り込まれており、なかなかシリアスな面も多い。
たとえば雑貨屋のアイおばさんはムサシに非常によくしてくれるのだが、このアイおばさんは夫を過去に事故で失くしており、一人息子のテムを女手一つで育てている。息子のテムもまた、一見するとただの元気でやんちゃな子供なのだが、父親の死もあって気丈にふるまっていることが分かる。
また、酒場でいつも飲んだくれているパン屋のブレッドという人物がいる。彼は妻を亡くしたせいでダメ人間になってしまった。
武蔵伝にはこのような人死ににまつわる過去をもつキャラクターが多く登場する。こういった設定の生々しさはキャラクターをより彩ってくれる。
多くの人物はムサシに対して元気に仲良く接してくれるので、その裏にこういった背景があるということがより際立つのである。
裏設定の多い悪役たち
本作の大きな敵役として「ル・コアール帝国」が用意されている。
彼らは「ヤクイニック王国」に攻めてきただけでなく、本作のヒロインであるフィーレ姫を誘拐するという分かりやすい悪役である。しかし実のところ、彼らはラスボスではないし、戦う回数もそこまで多くは無い。
ムサシは帝国にさらわれたフィーレ姫を取り戻すため、各地に眠るクレスト=ガーディアンを倒し、伝説の剣レイガンドの封印された力を取り戻しにいく。
どちらかというとこのクレスト=ガーディアンがポスとして目立つ。
そのうえ、ラスボスは過去のムサシに封印された魔人レイガンドであり、記憶を失っているムサシ本人に封印を解かせていたという衝撃の事実も判明する。
さらにはムサシにずっと協力してくれていた人物の意外すぎる過去が判明したり、ストーリーが進むにつれて帝国の影が薄くなっていく。
そんな彼らも基本シリアスでありながらコメディ要素がふんだんにあり、憎めない名悪役となっている。そして彼らは裏設定がとても多い。
たとえばムサシとよく対峙する「リーダーズフォース」。彼らは全員が自分をリーダーと思い込んでいるからリーダーズという憎めない名前の部隊なのだが、彼らは全員が帝国の英雄召喚によって呼び出された失敗作なのである。
エドは江戸川五右衛門、ベーンは武蔵坊弁慶、トポは女ネズミ小僧、全員ムサシと同様に子供の姿で召喚されてしまった。
ほかにも皇帝の実息であるムキムキ鉄仮面のボルドー少尉。彼は最初のボスとして登場し、作品にコメディを振りまく要因として出てくるのだが、本来は病弱体質であり、それを補うためにドーピングのために鉄仮面を付けている。
公式攻略本の解体真書では、ED後のストーリーとして、彼が鉄仮面を外し帝国を再建することを決心する話が挿絵とともに描かれている。
こういった設定は本編では語られていない。
そこに対しては賛否両論ある。しかし設定が深く練り込まれているが本編で語られていない作品には「ニーア」など有名なものもあり、作品が長く語り継がれ、考察される要因でもある。
ここでは語りきれないが、こういった裏設定をもつキャラクターは他にも数多く登場する。
もちろん、そんな設定を知らなくても十分に楽しめるし、それを本編中で匂わせ考察できるようには工夫されている。
大貫健一さんの漫画版「ブレイヴフェンサー ムサシ伝」
本作武蔵伝は「ブレイヴフェンサー ムサシ伝」という名で漫画化されている。
作者はゴールデンカムイなどを手掛けるアニメーターの大貫健一氏である。
全3巻で構成されており、ムサシがゲーム版より少々ヤンチャになっていたり、全体のストーリー構成も大幅に変更されている。
しかしながらストーリー自体は良くまとめられている。大事な設定はすべて拾っているし、おおまかな話の流れも同じとなっている。ウォッカ大佐とジャンなど重要な人物に対しても深く掘り下げられているし、構成力が素晴らしい作品だ。
ちなみにフィーレ姫はとても可愛く描かれている。
まとめ:細部まで作り込まれた丁寧なリアルタイム箱庭アクションRPG
正直まだ半分も語れていないのだが、今回はこの辺りで終わろう。
リアルタイムに時が流れる世界、できることも種類も多いスキルやアクションの数々、ほぼ全てのキャラクターに用意された詳細なプロフィールと裏設定。
これほど製作者の愛が隅々まで詰まり、かつゲームも骨太なものは珍しい。
FF8の体験版が付属されたゲームとして有名になったゲームであるが、その作り込みには多くのプレイヤーが驚嘆し、のめり込んだことだろう。
公式ホームページからアーカイヴ版を購入できるので、興味がある方はぜひともプレイしてみてほしい。